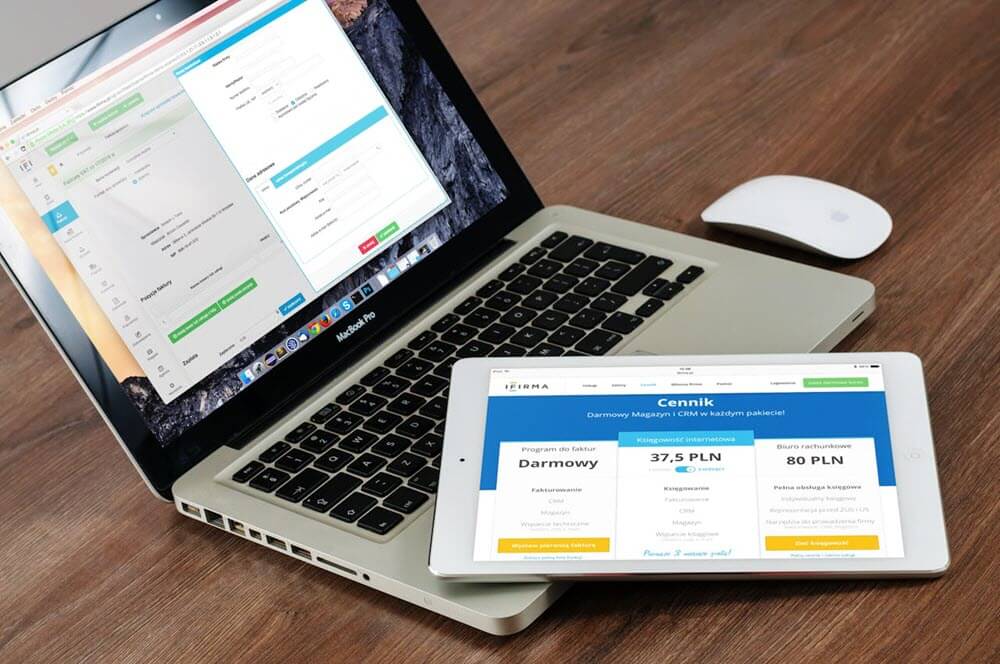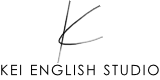東南アジア向け越境ECは自社サイトよりもFacebookやTikTokマーケティングが効果的?

はじめに:東南アジア市場が今注目される理由
近年、越境ECのターゲット市場として「東南アジア」が強く注目されています。理由は明確です。高い経済成長率、スマホ普及率の急上昇、そして20〜30代の若い人口比率の高さです。特にベトナム、フィリピン、インドネシア、マレーシア、タイなどは、国内市場の飽和に悩む日本の中小企業にとって“希望の地”となりつつあります。
しかし実際に東南アジア市場へ商品を売ろうとすると、次のような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
- まずは自社サイトを作ればいいのか?
- 現地で流行っているSNSでプロモーションした方がいいのか?
- Shopifyなどのプラットフォームが必要なのか?
本記事では特に、「自社サイト vs SNS(FacebookやTikTok)」という視点から、東南アジア向け越境ECにおける最適な戦略について解説します。
東南アジアは“自社サイト文化”が根付いていない?
まず最初に確認しておくべき事実があります。それは、日本人が一般的に想像するような「公式サイトから購入する」という購買行動が、東南アジアではあまり主流ではないということです。
特に都市部以外のユーザーは、「Web検索 → ECサイトにアクセス → 商品比較 → 決済」という導線よりも、次のような行動パターンを好みます。
- Facebookで商品画像を見る
- コメント欄で質問する
- Messengerで直接販売者とやり取りする
- 現金代引き(Cash on Delivery)で購入
つまり、東南アジアでは「SNSそのものが販売チャネル」になっているのです。特にFacebookは「ショッピングモール+LINE+ECサイト」が合体したような機能を果たしています。
Facebookマーケティングの現地での実情
1. 実際に売れているのは「Facebookページ+Messenger販売」
東南アジアの多くの小規模ビジネスや個人販売者は、公式Webサイトを持たず、FacebookページとMessengerだけで販売を完結させています。商品の紹介は画像やリール動画を活用し、注文はDMで受け、支払いは銀行送金(最近はGCashという送金アプリ)または代引き。
日本のようなカートシステムは不要で、会話ベースの販売がスタンダードです。この「チャットコマース」の文化は、タイ、ベトナム、フィリピン、インドネシアなどで強く根づいています。
2. 有料広告の費用対効果が非常に高い
日本と比べてFacebook広告のCPC(クリック単価)が非常に安いため、少額でも十分な反応が得られます。実際に1,000円〜2,000円程度の広告費で数十件のDMを獲得できた例もあります。
重要なのは「広告からWebサイトへ誘導する」よりも、「広告からMessengerへ誘導する」形式の方がコンバージョン率が圧倒的に高いという点です。
3. 決済方法は「現金代引き」が圧倒的に強い
日本のようにクレジットカードやPayPayでスムーズに決済できる国はまだ少数派です。特にインドネシア、フィリピン、ベトナムでは、代引き(Cash on Delivery)の信頼性が高く、多くのユーザーがこれを希望します。
したがって、自社サイトでクレカ決済のみを用意しても「買いたいのに買えない」ユーザーが大量に発生してしまいます。
TikTokの急成長と“ライブコマース”の衝撃
東南アジアでは、TikTokも越境ECの重要チャネルになりつつあります。TikTokには独自の「TikTok Shop」機能があり、動画やライブ配信中に商品を紹介して、その場で購入へ誘導できます。
1. ライブ配信と同時に売る「エンタメ型販売」
タイやマレーシアなどでは、ライブ配信で商品を紹介しながら、コメントで質問に答え、リアルタイムで注文を受ける形式が広く使われています。いわゆる“ライブコマース”です。
このスタイルは「売り手の人柄」や「使い方の実演」が伝わりやすく、信頼感の獲得につながりやすいのが特徴です。日本のテレビショッピングと似ていますが、より双方向的でリアルタイム性が高い点がポイントです。
2. 動画編集より「人柄・臨場感」が重視される
日本では丁寧に編集された動画やイメージ重視のCMが好まれますが、東南アジアではスマホで撮影されたラフな動画やリアルな配信の方が好まれる傾向があります。よって、高度な撮影機材や編集スキルは必須ではありません。
自社サイトが不要というわけではない
ここまで読むと「もう自社サイトは要らないのでは?」と思う方もいるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。以下の理由で、むしろ中長期的には自社サイトの整備が不可欠です。
- 広告アカウントがBANされるなど、SNSに依存しすぎるリスクがある
- ブランドの信用力を高めるためには公式サイトが重要
- 詳細な商品情報、会社情報、Q&AなどはSNSでは表現しきれない
- 将来的にGoogle検索経由での流入も狙える
つまり、最初の集客やテスト販売はSNSが圧倒的に強力ですが、信頼性や長期的なブランディングには自社サイトが欠かせません。両者をバランスよく使い分けることが重要です。
おすすめの戦略:SNS先行型 → 自社サイト補完型
東南アジア向け越境ECをこれから始める中小企業にとって、次のようなステップがおすすめです。
ステップ1:Facebookページを作成し、商品を投稿
現地のトレンドに合わせた画像や短い動画を用意し、コメント欄やMessengerで注文を受けられる体制を整えます。ターゲット国の言語(英語、ベトナム語、タガログ語など)を使うことも忘れずに。
ステップ2:少額からFacebook広告をテスト
CPCが安いため、1日500円〜でも十分に反応が得られます。最初は「Messenger誘導型」の広告が効果的です。
ステップ3:ライブコマースにも挑戦
スマホ1台でも始められるため、気軽に配信してみましょう。現地語を話せなくても、日本語で親しみやすいスタイルなら興味を持ってもらえるケースも多いです。
ステップ4:自社サイトを構築して信頼性を補強
ある程度注文が安定してきた段階で、ShopifyやWooCommerceを使って自社ECサイトを構築します。商品の詳細情報や配送ポリシーなどをしっかり記載し、広告やSNSからの導線も整えます。
まとめ:東南アジア向け越境ECは“SNSファースト”が基本
東南アジア市場は、日本とは文化も購買行動も大きく異なります。特に重要なのは「公式サイトよりSNSが主役」という現実を理解し、それに合わせて販売戦略を組み立てることです。
自社サイトからスタートする従来の方法では、反応が得られにくく、成果が出るまでに時間と費用がかかる可能性があります。まずはFacebookやTikTokなど、現地で使われているSNSを活用して実際の反応を見ながら、柔軟に施策を調整していくことが現実的なアプローチです。
マーケティングは「相手に合わせる」ことから始まります。あなたの会社が誠実に、現地のユーザーとコミュニケーションを取りながら販売活動を続ければ、必ず道は開けるはずです。
越境ECサイトの無料相談を行っています!
「まずは話を聞いてみたい」「予算内でできるか相談したい」など、お気軽にお問い合わせください。
Zoomまたはメールで無料ヒアリングを実施中です。