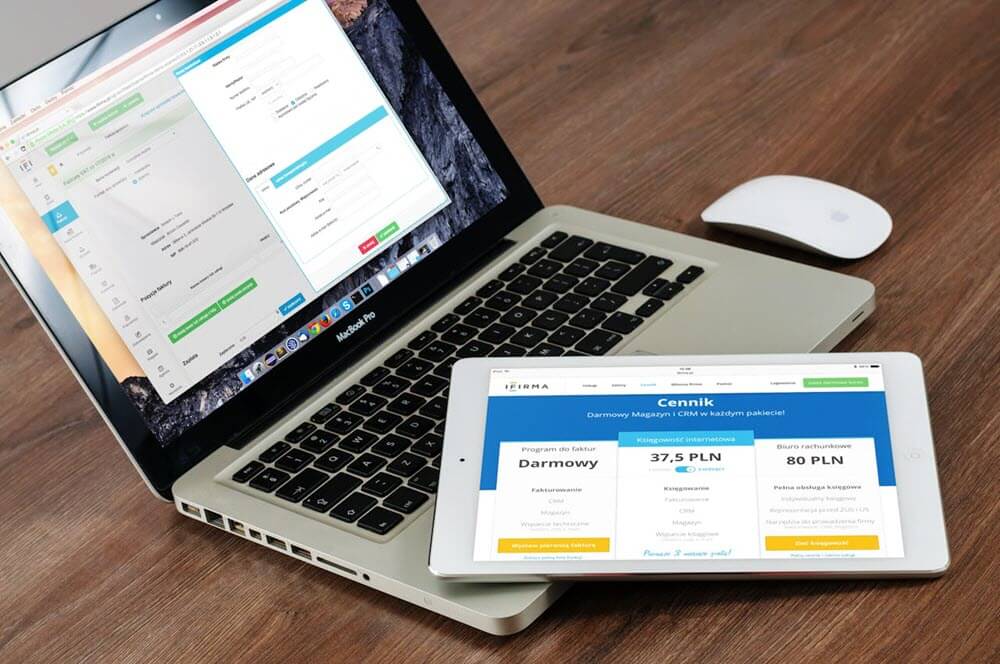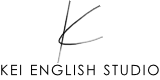フィリピンから見た越境EC市場のリアル

東南アジアの中でも注目されることの多いフィリピン市場。英語が通じる、若年層が多い、親日的――こうした特徴から「越境ECの狙い目」と語られることもあります。
しかし、実際にフィリピンに住み、現地の生活者やネット環境、物流事情、消費文化に触れている立場から見れば、それらの評価には現実とのギャップも存在します。
この記事では、フィリピンに住む制作者の視点から、「越境EC市場としてのフィリピンのリアル」について、表も裏も含めて正直に解説してまいります。
フィリピン市場が「期待されている」理由
英語が公用語
フィリピンの最大の強みのひとつは、国民の大半が英語を話せるという点です。教育やビジネスも英語が基本となっており、越境ECにおける多言語対応のハードルが低いとされています。
人口と成長性
人口は約1億2千万人。東南アジアでもインドネシアに次ぐ大国であり、経済成長も続いています。中間層も年々増加しており、スマートフォン普及率も急速に高まっています。
親日的な文化
日本に対して非常に好意的で、「日本製=信頼できる」というイメージが強く根付いています。日本人観光客や移住者も多く、文化的な心理的距離が非常に近い国のひとつです。
こうしたポジティブ要素を背景に、「フィリピンは越境ECに向いている」という論調がネット上で散見されます。しかし・・・
フィリピン市場の“現実”に潜む壁
物流インフラの不安定さ
最大の壁は、物流です。特に地方都市や郊外では住所表記が不正確であったり、再配達の仕組みが機能していなかったりするケースが少なくありません。
国際配送でDHLやFedExを使っても、「住所不備」で返送されることが珍しくなく、EC事業者にとっては大きなリスクです。
自社ECサイトは信頼されにくい
フィリピンの消費者は基本的に自社ECサイトよりも、大手マーケットプレイスを信頼します。ShopeeやLazadaといったプラットフォームが圧倒的な存在感を持っており、「知らないサイトで直接買う」ことに対しては強い抵抗があります。
そのため、せっかく英語でECサイトを構築しても、購入にはなかなかつながらない――というケースが少なくありません。
決済事情と信用文化
クレジットカードの普及率は非常に低く、多くのユーザーは代引き(COD)を利用します。ECの支払いは「商品が届いてから払う」のが当たり前という感覚が根強く、事前決済はあまり好まれません。
さらに、フィリピンでは詐欺サイトや偽ブランド品の被害も多いため、「サイトで直接買うこと=リスクがある」という印象を持つ人も多いのです。
フィリピンの越境ECは“ゼロ”ではないが戦略が必要
まずはマーケットプレイスを活用せよ
フィリピン市場において海外販売を行うなら、自社ECサイトではなく、まずはShopeeやLazadaなど、現地で信頼されているマーケットプレイスへの出品が現実的です。
特にShopeeは、2023年時点でフィリピン国内のEC利用者の70%以上が日常的に使っているとされ、ここに商品を出すことが最短の接点になります。
商品の選び方が重要
フィリピンでは、化粧品や美白系スキンケア、アニメグッズ、ファッション小物などが人気です。高額な家電や家具は配送・関税の関係で難易度が高いため、単価が中〜低価格で配送しやすい商材が好まれます。
また、感情に訴える商品説明、Before/Afterの写真、SNSでの実演紹介など、「映えるマーケティング」が効果的です。
現地とのパートナー連携
将来的に本格展開を視野に入れる場合は、現地のロジスティクス会社や販売代行業者との提携も選択肢となります。現地の市場感覚・販売チャネルを理解している企業と組むことで、リスクを抑えつつ販売が可能になります。
フィリピンに向いている企業・向いていない企業
向いているタイプ
- 低〜中価格帯の商品を扱っている
- 既にShopeeやLazadaなどの出品経験がある
- 英語の商品説明が準備できる
- 東南アジアに展開したいという長期的な視野がある
向いていないタイプ
- 高価格帯の商品をメインにしている
- 「自社ECで完結させたい」という考えが強い
- 配送品質に強いこだわりがある
- 即効性や短期的な売上を求める
フィリピンから見える越境ECの“本質”
フィリピンに住んでいると、「売ること」よりも「届けること」「信用してもらうこと」がどれほど難しいかを実感します。
つまり、越境ECとは単に「英語でサイトを作れば売れる」ものではなく、「現地の文化・信頼・流通・価値観に寄り添う設計」が必要なのです。
それはフィリピンに限った話ではありません。どの国であれ、ただ商品を並べただけのECでは信用されず、購入にはつながりません。
だからこそ、中小企業がフィリピン市場に挑む際には、戦略と忍耐、そして現地のリアルな声を理解する“共感力”が求められます。
まとめ:フィリピン市場は「知っている者だけが勝てる」
フィリピン市場は、確かに魅力的なポテンシャルを持っています。
しかし、その魅力は「表層的なデータ」や「海外販路の可能性」だけを見ていては見えてきません。実際に現地に住み、体感し、文化を理解して初めて見えてくる“複雑な現実”が存在します。
私はそのリアルを知っているからこそ、単なる楽観論ではなく、戦略的な越境EC支援をご提案できます。
もし「フィリピン市場を開拓したい」「東南アジアに本気で商品を売りたい」と考えている方は、どうぞお気軽にご相談ください。
越境ECサイトの無料相談を行っています!
「まずは話を聞いてみたい」「予算内でできるか相談したい」など、お気軽にお問い合わせください。
Zoomまたはメールで無料ヒアリングを実施中です。