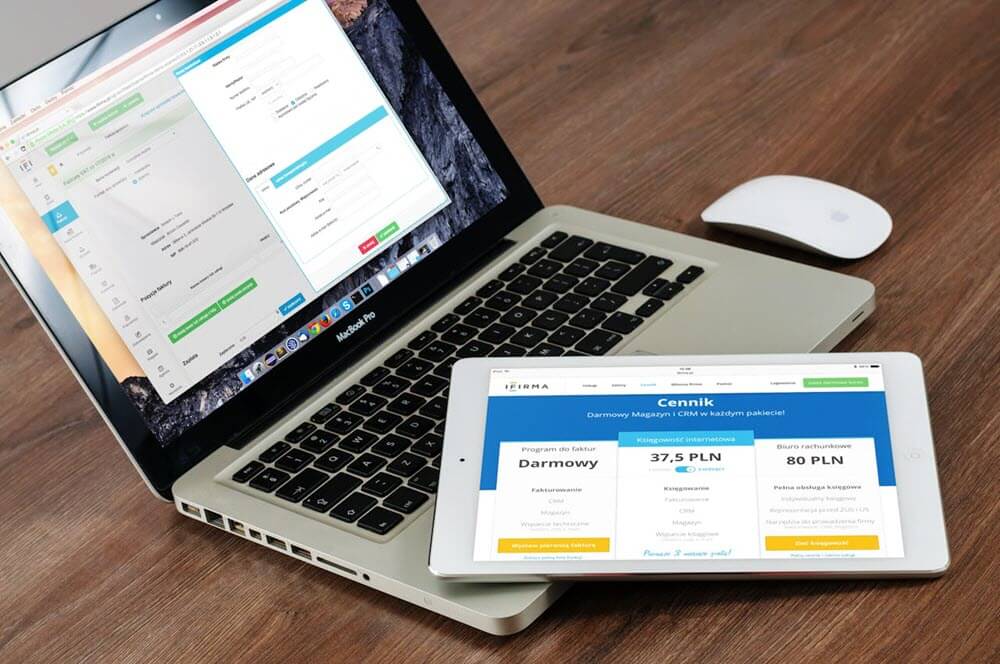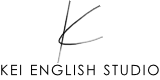フィリピン語学学校の教師に見る“見えない格差”の実態

フィリピンといえば、格安のマンツーマン英語レッスンが受けられる留学先として、日本人にも広く知られている。特にセブ島は「英語留学の聖地」と呼ばれ、年間数万人の日本人、韓国人、中国人学生が訪れる。だが、観光客や留学生には見えにくい、フィリピン語学学校の“内側の格差”について語られることは少ない。
筆者はかつてフィリピン・セブ島の語学学校に在籍し、1年以上にわたり複数の講師と日常的に接してきた。表面的には明るく親切な先生たちであったが、ふとした瞬間に見せる生活の違い、価値観の断絶、それこそが“見えない経済階層”の現実だった。
その後、フィリピン人と結婚しフィリピン社会で過ごす中で見えてきたあまりにも残酷すぎるどうしようもない現実が更に見えてきた。しかしフィリピン人全てが悲惨という訳ではない。むしろその逆。実際は過半数以上のフィリピン人が豊かさを享受している。しかし、それから取り残されたフィリピン人は悲惨で過酷な日々を過ごしている。
同じ給与、まったく違う生活水準
語学学校の講師たちは、おおむね月給6万円程度で働いている。この額はフィリピンの一般的なオフィスワーカーよりは遥かに低いがモールの飲食店で働くサービス業よりは若干高いという額であり、いわば中間層の底辺レベルと言える。
しかし、驚くべきことに、同じ学校で、同じ業務、同じ給与で働いている講師たちの生活水準は「天と地ほども違う」のである。ある講師は貧困の極みに暮らし、もう一人は毎日レストランでランチを食べ、高級スマートフォンを持ち、休日はビーチリゾートへドライブに出かけている。いったい何がこの差を生んでいるのか?
事例1:OFW(海外出稼ぎ労働者)がいない家庭の講師A(月収6万円)
講師Aは筆者の担当講師のひとりで、誠実で真面目な性格だった。だが彼女の生活はあまりに過酷だった。月給6万円はまともな生活をするには少なすぎた。ランチはスラム街によくあるカレンデリア(大衆食堂)。スラム街にあるのでハエやゴキブリがうようよいてハエと戦いながらご飯を食べるような環境だ。(時にはハエが混じったご飯を食べていたかもしれない)
通勤はジプニー(フィリピンの庶民バス)を2本乗り継ぎ、1時間半かけて学校に来る。授業中は笑顔だが、ふとしたときに疲れた顔を見せることがあった。授業中に家族の話や子供の話も聞いたがかなり辛そうだった。講師がランチで食べているあの悲惨な食事から察するに家族もまともなご飯は食べていないだろうと簡単に想像できた。
事例2:OFW(海外出稼ぎ労働者)がいる家庭の講師B(月収46万円)
一方、講師Bはまるで別世界に住んでいるかのようだった。彼女もまた月給6万円の講師であるが、昼休みになるとレストランに出かけ、その後はカフェでフラペチーノを片手にリラックス。服装はいつも清潔で流行を押さえ、iPhoneの最新モデルを所持。通勤は自家用車で、帰宅後は自宅でNetflixを見て過ごす。
その違いの理由はただひとつ。「親族にOFW(海外出稼ぎ労働者)がいるかどうか」である。講師Bの兄はアメリカで看護師として働いており、毎月20万円以上を実家に送金している。他にもカナダなどに家族がいて20万円ほど送金を受けている。月給は6万円。でも海外送金を足すと月収総額は46万円以上。それによって講師Bは、働いているというよりは“軽く社会参加している”だけであり、経済的な重圧はゼロに近い。
その講師はおしゃれなバーやカフェにいくのが趣味で学校が終わった後、ホテルの屋上のセブが一望できるおしゃれなバーに連れて行ってもらったことがある。バーでの注文もその講師のおごりだった。普通の日本人よりも裕福な暮らしをしているなぁと驚いたものだった。
月給6万円は“重要ではない”
この2人の例から分かるのは、フィリピンにおいては「給与=生活水準」ではないということである。収入の大半を構成するのは“自分の給料”ではなく、“親族からの送金”なのだ。だからこそ、同じ職場で働いているにもかかわらず、講師たちの間には生活の断絶、思考の断絶、文化の断絶が存在する。ハッキリいって会社からの給料は「おまけ」でしかない。
この格差は学校側から見れば「全員平等に雇っている」に過ぎない。しかし、現実には教室の外で食べるランチひとつとっても、“世界が違う”のである。これは日本人が見落としがちな、フィリピン社会の最も重要な本質のひとつである。
OFWネットワークの影響力
フィリピンの人口のうち、少なくとも70%以上が「親族にOFWがいる」と言われている。これらの家庭は、定期的に数万円〜数十万円単位の仕送りを受け取り、生活の基盤とし、国内の給与水準とは関係なく“中流以上の生活”を送っている。
問題は、残りの30%である。つまり、「親族に海外在住者がいない」家庭。彼らはスラムに住み、病院にも行けず、1日1食で飢えを凌ぎ、時には窃盗や詐欺に手を染める。このように、フィリピンの最大の格差は“職業”ではなく、“家系”と“血縁”によって決定される。
外からの金が国内を支配している
フィリピン国内の購買力、消費行動、教育水準、医療アクセス、住環境――そのすべては、外から送られてくる金に依存している。言い換えれば、「外国にいる親族が何者であるか」が、人生のすべてを決定づける。
語学学校の教師たちを見ていると、それがよく分かる。彼らの笑顔の裏には、国家ではなく“家族”への依存と、“国外”への期待が詰まっている。そして、それは単なる願望ではなく、すでに“現実”として社会を動かしている。
まとめ:まるで貴族と奴隷が一緒の職場で共に働くような異常な環境、しかしこれがフィリピンの縮図。
語学学校という「閉じられた教育空間」は、実はフィリピン社会の“格差の縮図”でもある。日本人から見れば、講師たちは皆一様に「フィリピンの先生」であり、親切で丁寧な指導者である。
だが、その背後には、「自力で生きる者」と「他力で生きる者」の断絶が存在し、その差は年々拡大している。給与ではなく送金、能力ではなく血縁――これがフィリピンという国家の実態であり、そこに気づくことこそが、真にこの国を理解する第一歩となる。
講師たちは同じ制服を着て、同じ教科書を持って教壇に立っている。だがその胸の内に流れる“通貨の出所”は、まるで別の惑星から来たかのような違いを生んでいる。
越境ECサイトの無料相談を行っています!
「まずは話を聞いてみたい」「予算内でできるか相談したい」など、お気軽にお問い合わせください。
Zoomまたはメールで無料ヒアリングを実施中です。